今回は茨城県立高校入試の、「数学」の出題傾向について考えてみます。実は数学もかなり「記号」で回答させる問題が増えました。今年(2024年)の問題では、11問も記号で答えさせる問題がありました。私の時代や現在、親となっている世代では記号で答えさせる数学と言っても、ピンとこないと思います。大学入試であればマークシート形式というものもありますが、高校入試では珍しいものです。茨城県は数学での記号解答形式を本格的に取り入れております。

とは言え首都圏においては、東京や神奈川ではマークシート形式ですし、千葉県も2024年からマークシート形式に変わりました。これからはこの形式が標準となって行きそうなことを考えると、茨城県も近いうちにマークシート形式に変わるんだろうと思います。解答形式についてはこれくらいにしたいと思います。

次にどのような問題が今年、出題されたのかという事を検証したいと思います。分野的には、計算問題、小問集合問題、平面図形、確率問題、関数の文章問題、空間図形という形で大問6問構成でした。出題の分布は全体的にまんべんなく出題されていました。作図はなかったですが、一応、作図も練習しておいた方が良いと思います。作図は出題形式の変更が行われてから、採点のブレをなくすためか出題されなくなってはいますが。
では、数学の対策はどのようにしたら良いでしょうか?基本的にはまずは、「計算」を正確にできるようにしておくことが重要です。今年も配点には20点ありました。この20点は必ずゲットしましょう。その次が小問集合問題です。こちらも配点が20点です。このあたりを確実に取れれば40点もらえます。数学が苦手な人はこのあたりを徹底的に頑張りましょう!

計算系の問題以外の問題は、大問3の平面図形、大問4の確率、大問5の関数の文章問題、大問6の空間図形です。これらの問題は、どの大問も15点という配点です。数学が苦手な人は少しでも自分の得意なものから解くと良いと思います。また、空間図形というと難しく感じますが、「ねじれの位置」など知っていれば解ける問題もありますので諦めずに頑張りましょう!一般的には、数学が苦手な生徒さんは「確率」から解いてみると良いと思います。順当に手をつけるならば、確率→関数→図形の順になると思います。この辺りは過去問を解いてみて、自分の好みで決めると良いと思います。また、「平面図形」に含まれている「証明問題」は最近は穴埋め形式となっていますので、比較的取りやすいです。このあたりも正解できるように勉強してゆきましょう。
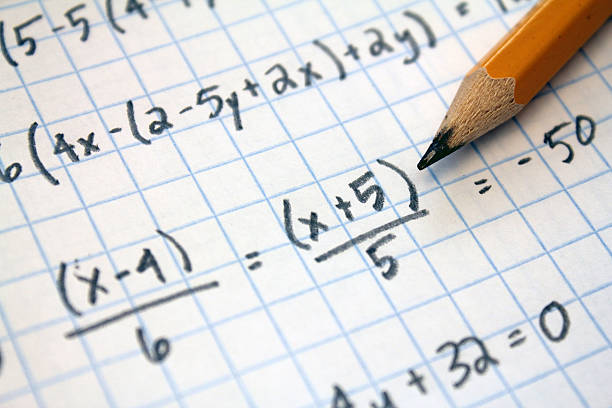
また、茨城県は難問が空間図形と平面図形のところに入っている場合が多いです。どんなに数学が得意な生徒さんでも、解答が思い浮かばないときは次の問題にうつってみることをお勧めいたします。受験は点数をなるべく多く得るものですので、手間のかかる問題はなるべく後回しにして、最後の最後の時間に解くようにしましょう。順番にサクサク解けるほど甘くないのも入試です。時には順番を変えて確実に取れる問題を解いて、見直しをして、点数を確保してから残りの時間で難問を解くという練習をしましょう。よって、あらかじめ目処をつけて受験に臨むことが大切なのです。
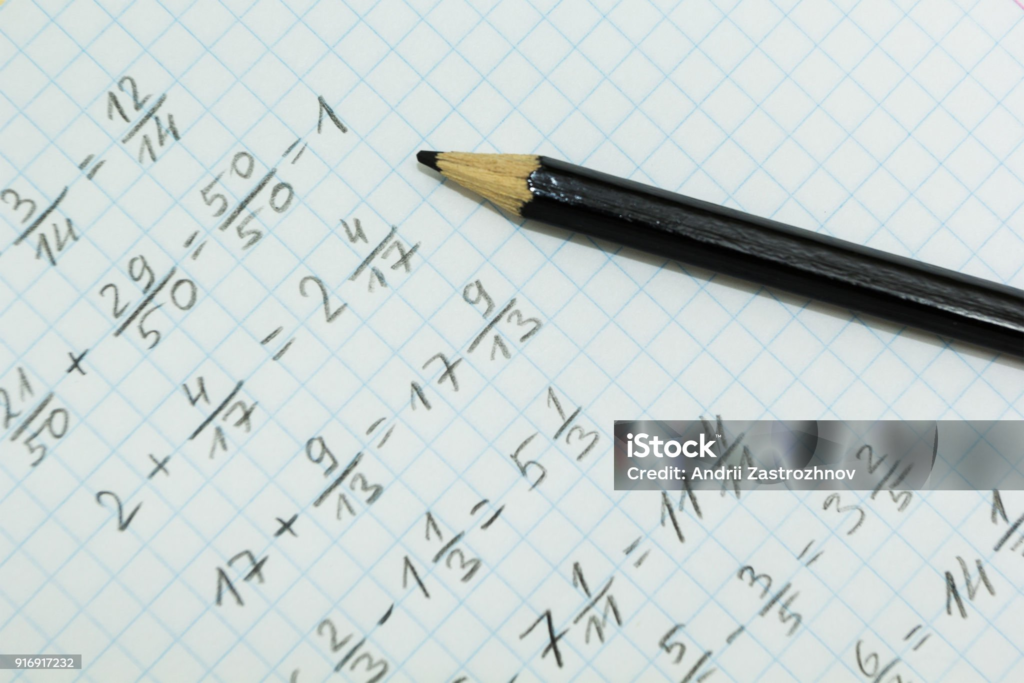
今回は茨城県の全体的な数学の出題傾向と2025年の出題に関して述べてみました。もし、あなたが、茨城県立高校入試で高得点を取りたいのであれば、この機会に城南コベッツ勝田教室の体験授業を受けてみて下さい!お申込み方法は簡単です。029(354)2544へお気軽にお電話ください。そして、「体験授業を受けたいです。」とお伝えください。ご連絡を楽しみにしております!一緒に頑張りましょう!


コメント