2月28日(水)に茨城県立高校入試が各高校を会場にして行われました。(特色選抜は翌29日も面接や実技の試験がありました。)城南コベッツ勝田教室の生徒さんも受験し、それぞれが日ごろの頑張りをたたえあいました。ここでは、2024年度の入試問題について、コベッツなりの分析を紹介したいと思います。

英語・国語・数学の3教科は、今までよりも解きやすく無理のない問題構成であったと言えます。コベッツ生も解きやすかったという感想の受験生が多かったです。英語では、何と単語を書かせるというのが無くなりました。受験生もビックリです。2は単語の記述だったのに、練習したのにという受験生が多かったです。数学は選択問題が11問に増えました。全体として解きやすい問題が多く、平均点が上がることが予想されます。

①<英語>大問の構成には変化はありませんでした。大問1のリスニングでは、不要語を含む選択問題が加わりました。今回のテストでの変化は、やはり何と言っても大問2です。問題形式が大きく変化し、書かせる問題から選択問題に変化しました。大問4は、情報機器の利便性についてが出題内容でした。本文、設問ともに新課程で加わった「現在完了進行形」が出されました。大問5は本文の抜き出しでした。全体の読解力の度合いも昨年までと変わらず、難易度に変化はなかったと思われます。
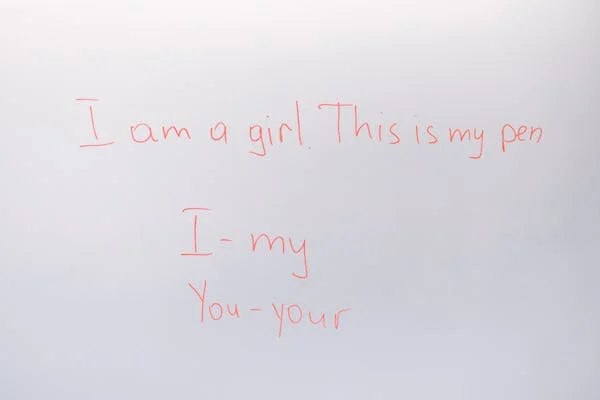
➁<国語>大問数は今までと同じ4問でした。ただし、出題の順序が変わりました。大問1は久しぶりに手紙文の問題でした。またそれに加える形で、漢字・慣用句などの知識問題が加わりました。大問2は高校生が主人公の小説と読んだ後の感想交流の読解問題でした。大問3は建築が主題の論説文とその内容をノートにまとめたものの読解問題でした。大問4は平家物語と漢文が出題されました。
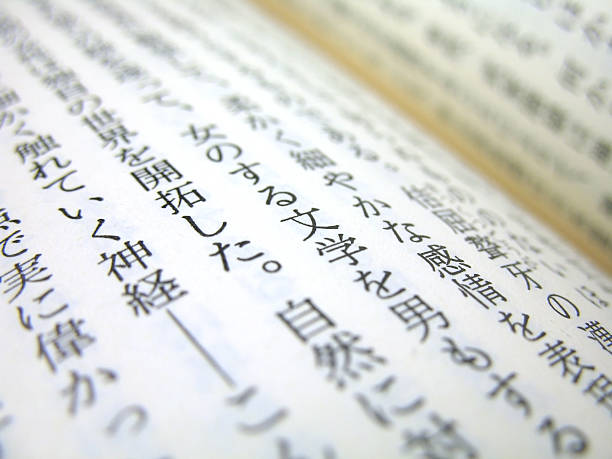
➂<数学>大問が6つというのは今までと同じでした。大問1の計算問題や大問2の小問題は例年通りの基本的なものでした。また、選択問題がかなり増えました。大問3の平面図形や大問5の一次関数は例年は難しい問題でしたが、今年は受験生にとって解きやすかったと思われます。一方、大問4の確率の中で、(2)➁は正答率が低かったと思われます。また、大問6の最後の問題は例年通りの難しさでした。しかし、全体としては選択問題が増えたこともあり、易しかったのではと思います。
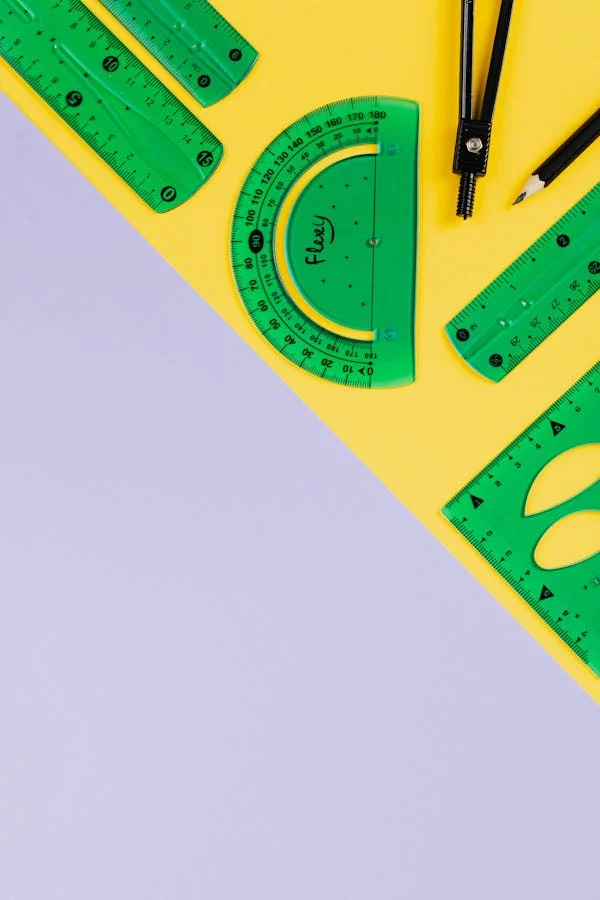
④<社会>大問の構成は今までと同じで、順番も変わらず地理・歴史・公民・3分野総合の順番でした。文章の記述は昨年度と同じ1問でした。文字数が5字以内から25字以内に増えたのですが、内容としては日比谷焼き討ち事件の起こった時の国民が不満をもった理由を説明させるもので、塾内でも正答率が高かったです。また、小問数が減り、配点が高くなったので正確に問題をこなしていく確実性が求められるものでした。設問形式は選択問題がほとんどでしたが、選択肢の数が多く、見た目よりも難しいところもありました。単純な知識事項や資料読解だけでなく、思考力が問われるものも増えました。よって、全体の難易度は今までと同じくらいであると言えます。

⑤<理科>大問構成は今までと同じでした。大問1がいつもの小問集合でした。大問2~大問5が各分野から1題ずつ、大問6が融合問題(物理と地学)でした。昨年までとの違いは、文章で答える記述問題が無くなったことと、計算問題が復活したことです。その中で、大問3のエタノールの質量を求める問題は、実験の結果と密度、質量パーセント濃度の意味の理解を求めるという、やや難しいもんだいでした。全体とは昨年度までと同じくらいの難易度だったと思われます。
2024年の茨城県の高校入試について(茨城統一テスト協議会の研修会より)




コメント